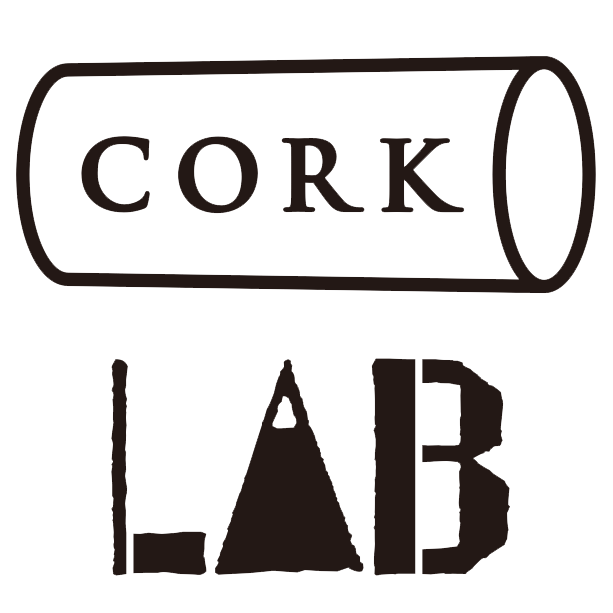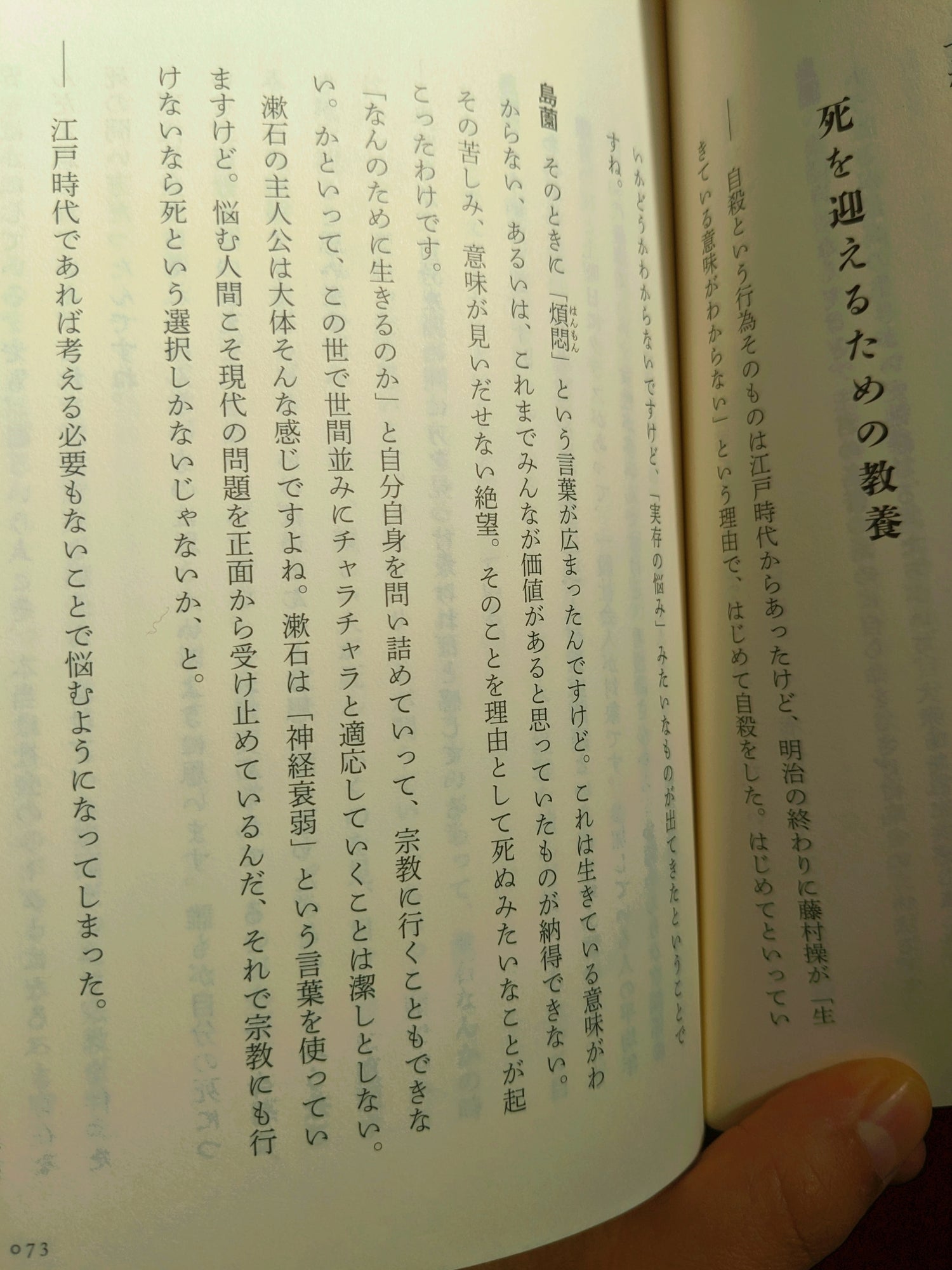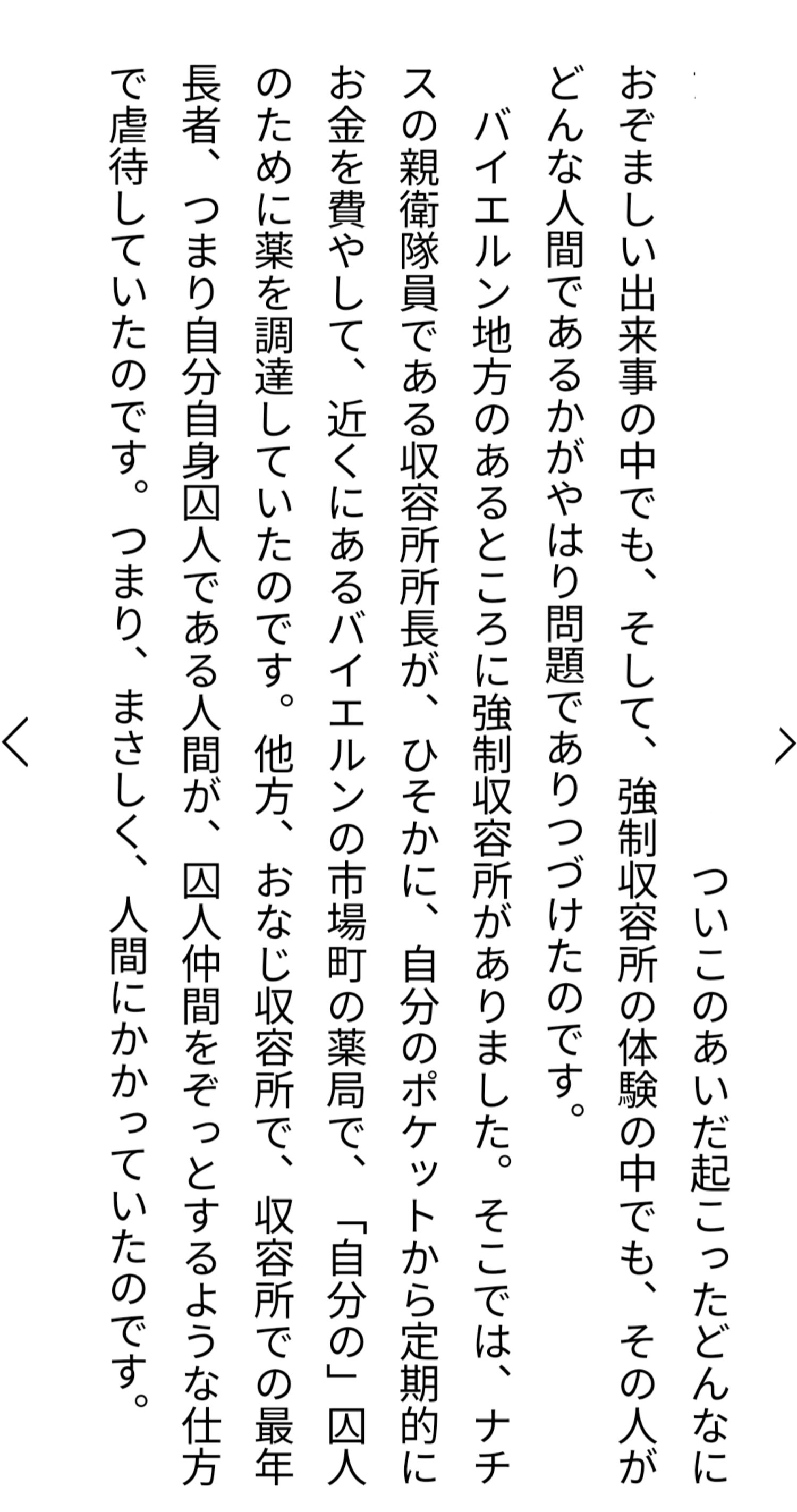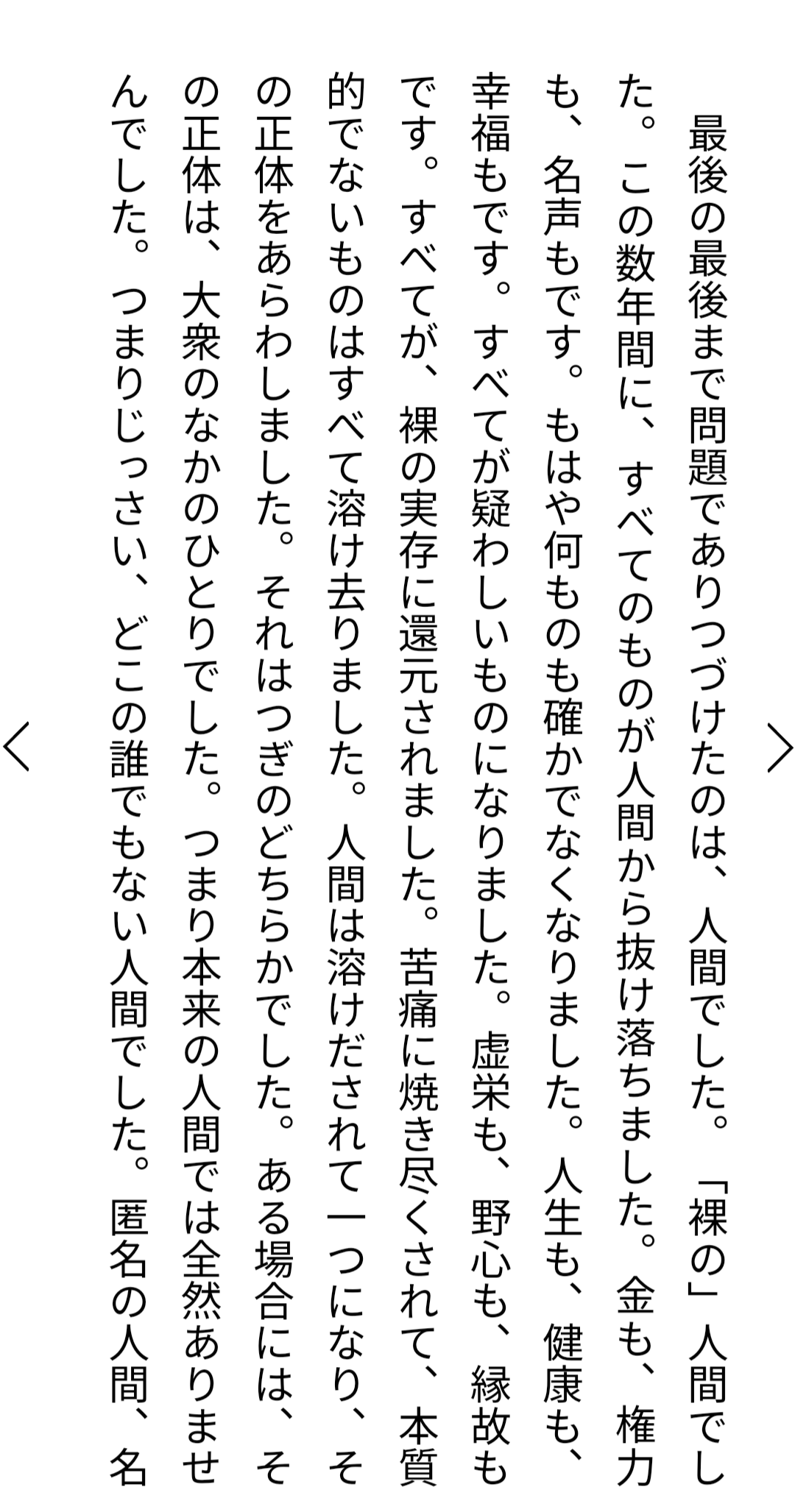「自分はなぜ生きるのか」という問いに、自分以外の他者はどう答えるだろう。
私は、以下のように考えているが、
「自分はなぜ生きるのか/自分であること(Be)」≠「自分は何者であるか(Do)」
「自分は何者であるか(Do)」という問いと「自分はなぜ生きるのか/自分であること(Be)」という問いが、イコールであると捉えられている場合が多いように感じる。
「自分はなぜ生きるのか」という問い
この問いは、実存の悩みである。
じつぞん【実存】
1.実際に存在すること。実在。
2.哲学
主観とか客観とかに分けてとらえる前の、存在の状態。ここに今あるということ。
明治の終わりあたりに、藤原操が「生きている意味が分からない」という理由ではじめて自殺をしたそうだ。
人間は、江戸時代では悩むことのなかったことで悩むようになったという。
そして、この悩みは宗教でも解決ができないものである。私自身も真言密教の総本山であるはずの高野山にいた頃に、「宗教でも解決できないのか...」と同じ局面にぶつかったことがある。
(「問うを学ぶ」より)
「自分はなぜ生きるのか」という問いは、即ち「自分であるということ」&「自分としてどう生きるのか」とほぼ同義の問いであると思う。
しかしながら、「自分が何者であるのか(Do)」ということと「自分であること(Be)」はまったく関係がないと私は考える。
「自分であること(Be)」のベースがないと「自分が何者であるのか(Do)」が変化すれば耐えられなくなる
これは、実体験として、心から思うことの一つだ。
「自分であること」の意味と、苦しみや痛みの意味を見出すということは同義であると思う。
(夜と霧の著者、ヴィクトール・フランクルが唱えていた思想である。)
最近、ヴィクトール・フランクルの「それでも人生にイエスと言おう」を購入した。
サンプルで読んでいたら、このページが気になった。
何もかもを奪ったナチスの強制収容所が唯一奪えなかったものが、「人間としての振る舞い方」のみであった。とヴィクトール・フランクルは夜と霧では、言っている。
結局のところ、残ったのは「裸の人間」であり、他のものすべて(名声、幸福、健康、人生、虚栄、野心、縁故も)が全て疑わしいものでしかなかったという体験を彼はしたのだとよくわかる文章。
何者かでなくなったら、自分でないのか?→答えはNOであると思う。
この問いは、NOであると答えられる。
が、ただ、実際に”何者でもなくなったことを経験していなかった時”は、「例え何者でなくなったとしても、自分は自分である。」とは、本当の意味では分かっていなかったなぁと思う。
「何者かである」ということは、現状やるべきことが目の前にあり、行動指針である自分の信念を携えている状態だ。
向かうべき何かがあり、そのためのTO DOを持っている状態とも言おうか。
この状態でいるときは、「何者でもなくなる」ということが実感としてはわからなかったな、と思う。
言葉の意味というのは、経験と共に持たされるものなんだろうなぁとしみじみ感じる。
ずっと、
「自分はなぜ生きるのか/自分であること(Be)」≠「自分は何者であるか(Do)」
について何か書きたいな〜と思っていたのだけど、今日書くことができてよかった📝